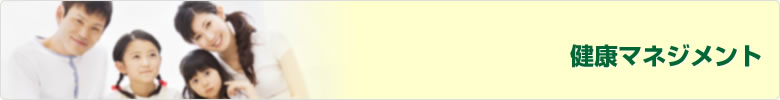東アジア原産で、中国や東南アジアでは古代から栽培されています。
日本へは中国から伝来したといわれ、「古事記」には神武天皇の段で「賀美良(かみら)」という名前で登場します。さらに平安時代の「本草和名」という薬物辞典には「韮の和名は古美良(こみら)」と記されています。ほかに「万葉集」や「延喜式(えんぎしき)」などの書物にも名前が出ててきます。
その頃は薬草として食べらるのがほとんどで、あまり普及していませんでした。
仏教では、臭いがきつくて精力がついてしまう野菜として、韮(ニラ)、大蒜(ニンニク)、葱(ネギ)、辣韮(ラッキョウ)、浅葱(アサツキ)を総称して五葷(ごくん)と言い、食べることがさけられていました。
長らく薬用として食べられていて、野菜として栽培されるようになったのは明治時代になってからだそうです。戦後はにんにくに次ぐスタミナ野菜として普及していきます。
ほぼ1年中店頭で販売されていますが、11月〜4月の間が、栄養も多くおいしいく食べられます。
新陳代謝を高め、血行をよくし、お腹をあたためるので、冷えによる腹痛にも効果があります。また、殺菌作用、滋養強壮効果もあります。
また、丈夫で作りやすく、刈り取った後の株から新しい新芽が伸びることと、特に寒い地方ではからだが温まり精力が付くと重宝されてきた野菜です。 |